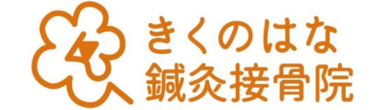偏頭痛はなぜ起こる?脳の反応とツボで読み解く
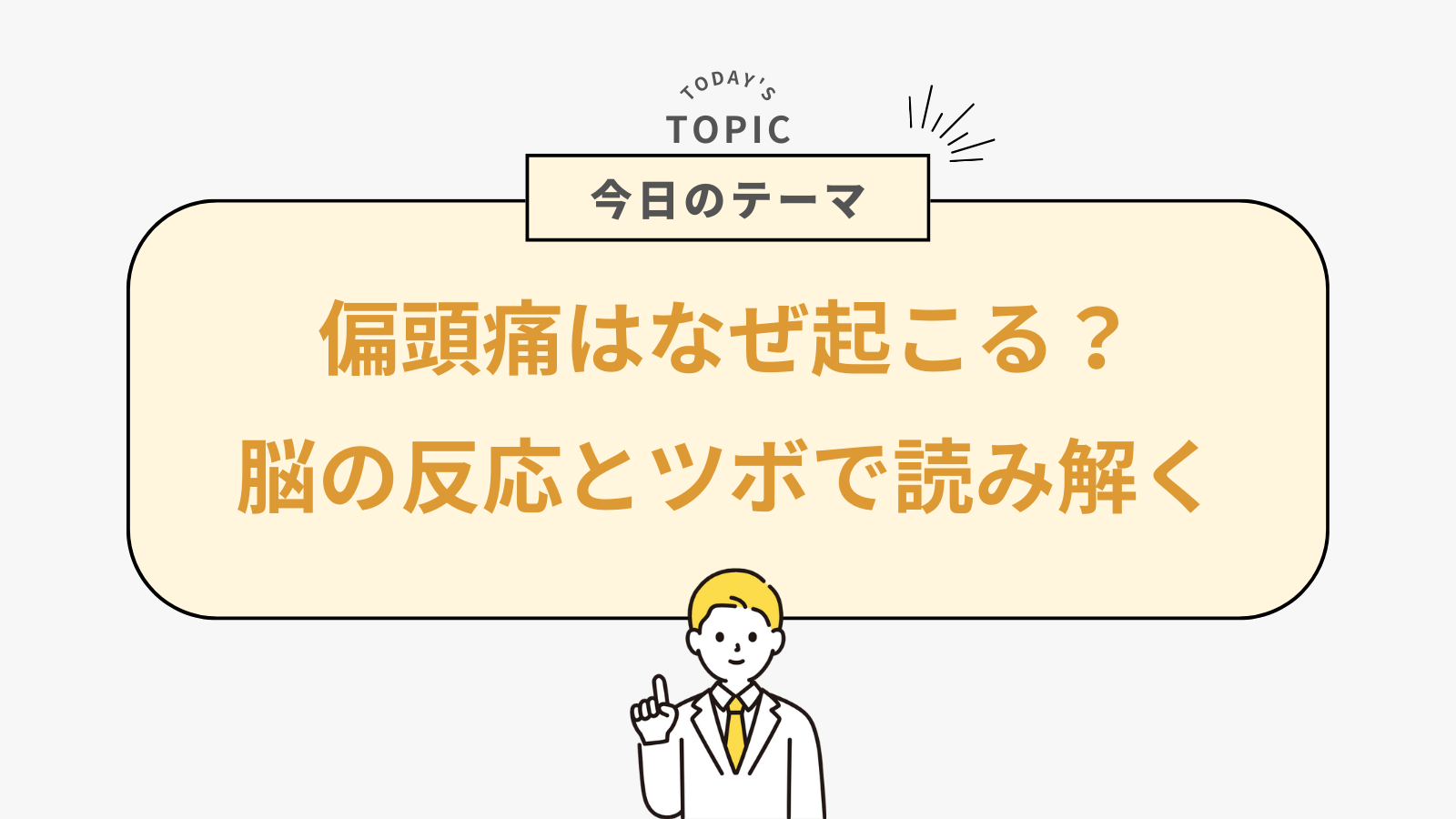
旅行に行きたいけれど、偏頭痛が心配で予定を立てられない。
天気が崩れそうな日は、なんとなく気分が沈んでしまう。
そんなふうに、「頭痛に振り回されている毎日」を送っていませんか?
「もう長年のことだし…」「年齢のせいかな…」とあきらめている方も多いかもしれません。
でも実は、偏頭痛には“明確なメカニズム”と“対処法”があるのです。
まずは、その仕組みから一緒に見ていきましょう!
偏頭痛とは?〜普通の頭痛とどう違うの?〜
「頭痛」と一言でいっても、実はその種類や原因はさまざま。
それぞれで対処の仕方が異なるため、まずは「自分の頭痛がどのタイプか」を知ることがとても大切です。
偏頭痛の特徴は?
偏頭痛は、脳の血管や神経が過敏に反応して起こるタイプの頭痛です。
特に女性に多く、20〜50代で発症することが多いとされています。
- 片側(時に両側)に起こるズキズキとした拍動性の痛み
- 吐き気や光・音に敏感になる
- 数時間から数日続く
- 日常生活に支障が出るほどの強い痛み
痛みが強くなると、動くことすらつらくなり、「薬を飲んでも効かない」「仕事や家事ができない」など、生活の質(QOL)を大きく下げてしまうことがあります。
他の頭痛と比べると?
| 頭痛の種類 | 痛みの特徴 | 原因 | 対応法 |
|---|---|---|---|
| 偏頭痛 | ズキズキ、拍動性、吐き気あり | 脳の血管・神経の異常反応 | 薬+生活改善 |
| 緊張型頭痛 | 重だるい、頭を締めつけられる | 筋肉の緊張 | ストレッチ・リラックス |
| 群発頭痛 | 一点がえぐられるような激痛 | 自律神経の乱れ | 特殊な治療が必要 |
偏頭痛は「脳の病気」ではありませんが、神経が非常に敏感になっている状態です。
「頭痛くらい…」とがまんしてしまいがちですが、
偏頭痛は、きちんと知ってケアすれば“コントロールできる”症状です。
次の章では、そんな偏頭痛が「どうやって起きるのか(メカニズム)」を詳しく見ていきましょう。
偏頭痛のメカニズム|“4つの段階”で進む
偏頭痛は、実は【4つのステージ】に分けて考えることができます。
1. 前駆期(発作の1〜2日前)
この時期は、まだ頭痛そのものはありません。
けれど、脳の奥深くにある視床下部(ししょうかぶ)という、ホルモンや自律神経をコントロールしている場所が活性化し、体に“なんとなくの不調”が現れ始めます。
- あくびが増える
- 甘いものが欲しくなる
- 気分が不安定
- なんとなく“来そうな気配”
この段階で「あ、そろそろ偏頭痛が来るかも」と気づけると、早めの対処や予防が可能になります。
ご自身の“サイン”を知っておくことがとても大切です。
2. オーラ期(30〜60分前)
偏頭痛のある方のうち、約20〜30%にみられる特徴的な現象です。
この時期は、脳の視覚野や感覚をつかさどる部分が一時的に異常をきたすことで、目や体に違和感が出てきます。
- 視覚異常(光がチカチカ、ギザギザが見える)
- 感覚異常(手足のしびれ、ろれつが回らない)
これは脳の「後頭葉」で起こる皮質拡延性抑制(CSD)の影響と考えられています。
この現象は、**「皮質拡延性抑制(CSD)」**と呼ばれる、脳の電気的な興奮と沈静の波が原因と考えられています。
オーラは一時的ですが、初めて体験するとびっくりされる方も多いです。
慣れてくると「オーラが出たから、そろそろ痛くなる」と判断材料にもなります。
3. 発作期(いよいよ痛みが出る)
ここでようやく、「ズキズキ」「ドクドク」とした偏頭痛特有の痛みが出てきます。
このとき脳では、**三叉神経(さんさしんけい)**が活性化し、「CGRP(カルシトニン遺伝子関連ペプチド)」という物質が放出されています。
このCGRPが血管を拡げ、まわりの神経や組織に炎症を起こすことで、激しい痛みや吐き気、感覚過敏といった症状につながるのです。
📌 この「CGRP」は、近年の偏頭痛治療において非常に重要なキーワードであり、
対象をピンポイントに狙った新しい注射薬(CGRP阻害薬)も登場しています。
この発作期のタイミングで適切な薬を使えるかどうかが、偏頭痛の強さや持続時間に大きく影響します。
4. 回復期(痛みは治まっても…)
痛みが治まったあとも、「スッキリ元気に戻る」というよりは、
むしろ“脳が使い果たされてクタクタ”という状態になることが多いです。
- だるさ
- 眠気
- 集中力低下
この回復期も、偏頭痛の一部。
「終わったあとも1日ボーッとする…」「なんだか全身が重い」という感覚がある場合は、この回復期にあたります。
無理をせず、少し身体を休める時間を取ることが大切です。
偏頭痛の原因・誘因とは?
偏頭痛の発作を引き起こす要因(トリガー)は、日常の中にたくさん潜んでいます。
「気のせいかな…?」と思っていたことが、実は偏頭痛のきっかけになっていた、というケースも少なくありません。
よくある誘因
- 睡眠の乱れ(寝不足/寝すぎ)
脳は睡眠中に休息・整理整頓を行います。睡眠が足りなかったり、逆に寝すぎたりすると、脳が混乱し、偏頭痛を起こしやすくなります。 - 月経周期(女性ホルモンの変化)
特にエストロゲンの急激な変動が偏頭痛に影響するといわれています。排卵日前後や生理前後に頭痛が出る方は、このパターンが多いです。 - 空腹・血糖の低下
食事のタイミングが遅れたり、甘いものをとりすぎたあとに血糖値が急降下すると、脳のエネルギー不足が引き金となって偏頭痛を誘発することがあります。 - ストレスの解放(緊張が抜けた週末など)
意外にも、「ホッとしたタイミング」で偏頭痛が起こることも。これは、ストレス中に緊張していた神経や血管が緩むことで、バランスが崩れてしまうためです。 - 特定の食品(赤ワイン、チョコレート、ナッツ、チーズ)
これらの食品には、チラミンやヒスタミンといった偏頭痛を誘発する成分が含まれていることがあります。
「食べた翌日に頭が痛い」と感じたら、記録をつけてみるのもおすすめです。 - 気圧や気温の変化
台風や梅雨の季節、急な寒暖差などで、体が環境に追いつかず、自律神経が乱れることがあります。その結果、偏頭痛が誘発されることもあります。
最近注目されているのは「身体の状態」と偏頭痛の関係
近年では、「脳の異常」だけでなく、身体的なストレスも偏頭痛に深く関わっていることがわかってきました。
- 姿勢の悪さ(猫背・巻き肩)
長時間スマホを見る・パソコン作業をする…などの習慣で、首から肩まわりの筋肉が硬くなり、頭を支えるバランスが崩れます。このことが、頭の重さを三叉神経に伝えやすくし、偏頭痛につながることがあります。 - 首・肩まわりの緊張
ストレスがかかったり、冷えて血流が悪くなると、首や肩の筋肉がこわばります。
この筋肉の緊張が、神経を刺激して偏頭痛を誘発することがあるのです。 - 顎関節の歪みや噛みしめ癖
「朝起きたときにあごが疲れている」「無意識に歯を食いしばっている」そんな方は、顎関節まわりの緊張が三叉神経に影響している可能性があります。
こうした身体的な緊張や歪みが、「脳」と「神経」のはたらきを過敏にし、偏頭痛の誘発につながるケースが増えています。だからこそ、偏頭痛ケアは「頭」だけでなく、「身体」からのアプローチもとても大切です。
現在の治療法|薬との上手なつきあい方
「薬は飲みたくないけど、どうしても痛い…」
「できれば自然に治したいけど、日常生活に支障が出る…」
そんな時、正しい知識を持って選択肢を広げておくことがとても大切です。
偏頭痛は、薬をうまく使うことで“コントロールできる”疾患ともいわれています。
ここでは「急性期の薬」と「予防薬」について、わかりやすくご紹介します。
急性期の薬(発作を抑える)
偏頭痛のズキズキが始まってしまったとき、
「今の痛みを早く抑えること」が目的になります。
早めに飲むことで、痛みのピークを防いだり、持続時間を短くすることが期待できます。
| 種類 | 内容 |
|---|---|
| トリプタン系 | 偏頭痛特有の薬。三叉神経と血管の反応を抑える。例:スマトリプタン |
| NSAIDs | 一般的な鎮痛薬(ロキソニンなど)も効果あり |
| エルゴタミン製剤 | 古くからあるが副作用多め。今はあまり使われない |
💡ポイント
トリプタン系は「偏頭痛の始まり」に飲むのがベスト。
飲むタイミングが遅れると、効果が薄れることがあります。
予防薬(発作の頻度を減らす)
「月に何度も偏頭痛が起きてつらい…」
「発作のたびに仕事や家事が止まってしまう」
そんな方には、発作を“起こりにくくする”ための予防薬という選択肢があります。
| 種類 | 内容 |
|---|---|
| 抗てんかん薬(バルプロ酸など) | 神経の興奮をおさえる働きがあり、 偏頭痛の頻度や強さを軽減する。 |
| β遮断薬(プロプラノロールなど) | 心臓の薬としても使われるが、 交感神経をおさえて偏頭痛の予防にも効果あり。 |
| 抗うつ薬(三環系など) | 気分や自律神経のバランスを整える作用があり、 偏頭痛に関わる神経の過敏性をやわらげる。 |
💡補足
これらの薬は、「気分が落ち込んでいなくても」使われることがあります。
脳や神経の“過敏さ”をおさえるために使われていると理解してください。
⑥ セルフケア|偏頭痛にやさしい「ツボ」
「薬以外の方法で少しでも楽になりたい」
そんな方に、東洋医学の視点からのセルフケアをご紹介します。
🌿 ツボ①:風池(ふうち)
場所:後頭部の髪の生え際、うなじのくぼみ
効果:首こり・自律神経の乱れ・頭痛全般に
押し方:指でじんわり3〜5秒、ゆっくり深呼吸しながら
🌿 ツボ②:太陽(たいよう)
場所:こめかみの少し後ろ、ややくぼんだ所
効果:側頭部のズキズキ、目の疲れに
押し方:人差し指で円を描くように優しくマッサージ
🌿 ツボ③:合谷(ごうこく)
場所:手の甲、親指と人差し指の骨が交わるくぼみ
効果:万能の鎮痛ポイント。肩こりや顎の緊張にも
押し方:反対の親指で3秒×3回を目安に
ツボ押しの時間は1回3〜5分以内で十分です。
無理に強く押さず、「気持ちいい」と感じる圧で行いましょう。
⑦ まとめ|偏頭痛は「あなたのせい」じゃない
偏頭痛は、甘えでも、我慢のなさでもありません。
脳と体が「ちょっと過敏になっている」サイン。
だからこそ、理解してケアすれば、必ず変化は起きます。
- ちゃんとした仕組みがある
- 自分の体と向き合うヒントがある
- セルフケアでもサポートできる
「どうして私ばっかり…」と思っていた方も、
少しでも心が軽くなっていただけたなら幸いです。
もし、日常生活に支障をきたすような頭痛が続く場合は、
我慢せず、専門家に相談することも大切なケアのひとつです。
あなたの体は、あなたを守ろうとしてくれています。
どうか、優しく耳を傾けてあげてくださいね。