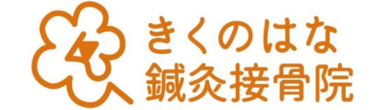【施術者向け】顎関節機能と姿勢への影響を考察
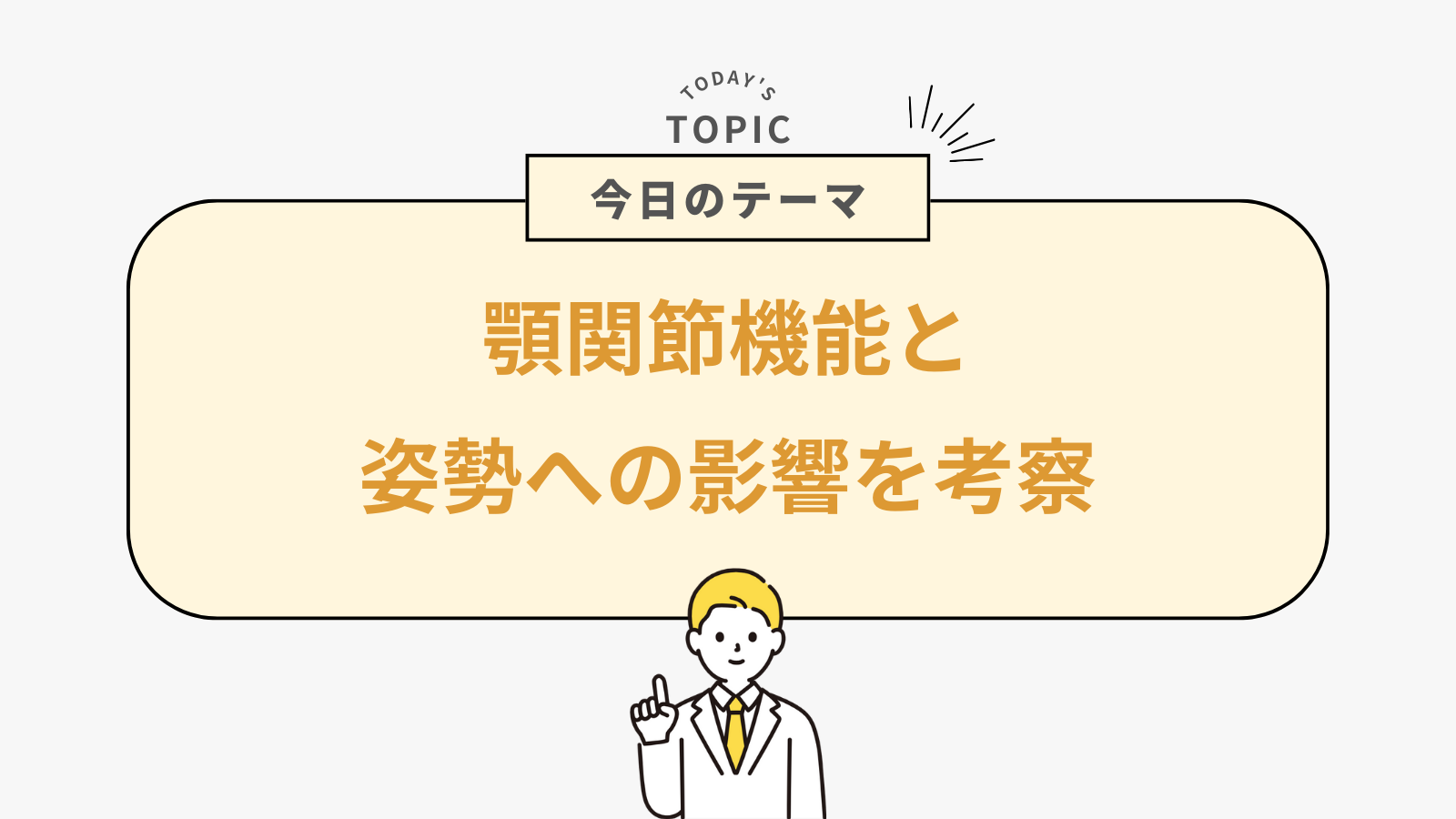
はじめに:なぜ今、側頭筋に注目するのか?
近年、顎関節症(TMD: Temporomandibular Disorders)を訴える患者が増加しています。その背景には、ストレス社会による噛みしめや歯ぎしりの増加、長時間のスマートフォン・PC作業による姿勢の悪化などが挙げられます。これらの習慣は、側頭筋をはじめとする咀嚼筋群に過度な緊張をもたらし、顎関節や頭頸部の不調につながることが明らかになっています(Murray, 2020)。
特に側頭筋は、閉口や顎の後退、側方運動といった多様な運動を担い、また頭頸部姿勢の安定にも関与するため、臨床において見逃すことのできない筋です。
側頭筋の解剖と走行の特徴
側頭筋(musculus temporalis)は、咀嚼筋の中でも最も広範な面積を持つ筋の一つであり、顎関節の運動制御のみならず、顔面~頭部の形態維持にも関与する重要な筋肉です。
◆ 起始・停止
- 起始:側頭窩(側頭線下部から蝶形骨の大翼外面にかけての側頭窩および側頭筋膜)
- 停止:下顎骨の筋突起(coronoid process)およびその下面の内側縁(場合によっては後方まで到達)
このように、頭蓋側面全体に広がる広い起始と、狭く絞られた停止部を持つため、筋束は扇状に配置され、複数方向の運動を同時に制御できる構造となっています。
◆ 筋束の分類と走行
- 前部線維:前頭骨側頭部から垂直に走行。主に下顎の挙上(閉口)を担当。高負荷時の咬合力発生にも寄与。
- 中部線維:側頭鱗部から斜め下前方に走行。閉口に加えて、軽度の後退運動に関与。筋突起に安定して収束するため、顎の回旋運動にも関与。
- 後部線維:側頭窩後方から水平方向に近く走行し、下顎を後方へ牽引(後退)する。咀嚼後や嚥下時の顎の安定に重要。
この三層的構造により、側頭筋は単一の筋でありながら三次元的な顎運動(上下・前後・左右)を制御できるという極めて機能的な構造を持ちます。
◆ 神経支配
- 支配神経:三叉神経(第V脳神経)の下顎神経(V3)の一枝である深側頭神経(nervus temporalis profundus)
- 前部・中部・後部すべてに分布し、運動制御を担う
- この神経は外側翼突筋の上を通過して側頭筋に到達
※ 臨床的には、深側頭神経が走行する経路は、翼口蓋窩からの神経交差部位で交感神経と関連するため、自律神経症状(耳の詰まり、頭重感など)とも間接的に関連するとする報告もあります。
◆ 血管支配
- 血管:深側頭動脈(maxillary arteryの枝)
- 筋内に豊富な血流を供給し、咀嚼時の高頻度な筋活動に対応
- 高度な緊張や慢性収縮では虚血→トリガーポイント形成の一因となることも
◆ 筋膜構造
- 側頭筋膜(temporal fascia):起始部を覆い、咬筋筋膜とも連結。頭皮・前頭筋・帽状腱膜との連続性があり、頭部全体の筋膜連動に関与。
- 特に頸部筋群(胸鎖乳突筋や僧帽筋)とも筋膜で連結しているため、頸肩部の姿勢不良が側頭筋の過緊張を引き起こす要因にもなりうる。
このように、側頭筋は単なる「咀嚼筋のひとつ」ではなく、顎関節、頭頸部姿勢、自律神経的影響までも含めた多面的機能を有する筋であることがわかります。
側頭筋の機能:三次元的な運動への関与
閉口運動(下顎の挙上)
咬筋、内側翼突筋と共に、下顎骨を上方に引き上げる働きを担いますが、特に側頭筋は閉口初期に最も早く活動する筋のひとつとされており(Koolstra & van Eijden, 2005)、咬合接触の微調整や歯列安定化にも関与していると考えられます。
また、閉口時の運動軌道では、関節頭が関節結節の後斜面を滑走しながら回旋運動を行うため、側頭筋の張力はこの運動を制御・安定化する重要な役割を果たしています。
顎の後退運動(retrusion)
口を開けた後、下顎頭は関節結節から後方へ戻るように滑走して閉口に至ります。このとき、側頭筋後部線維の収縮が必要不可欠であり、顎のニュートラルポジションへの復帰を補助する役割を果たします。
嚥下や会話時において、顎を安定させるための微細な後退調整が必要であり、後部側頭筋はその主要な動力源となります。
顎の側方運動(lateral excursion)
左右方向の運動では、一側の側頭筋が収縮し、同側への関節頭の滑走運動を制御します。これにより、反対側の外側翼突筋によって下顎が前方へ引き出される運動と連携し、咀嚼時の「グラインド運動」を可能にします。
このように、側頭筋は顎関節の回転(hinge)・滑走(glide)・側方運動(excursion)すべてに関与する高機能筋であり、顎の運動軌道の精密な制御を担っています。筋の左右差や過緊張があれば、顎偏位、関節音、疼痛などに直結するため、臨床評価の際にはこの三次元的運動を意識する必要があります。
顎関節との関係性:構造と機能から読み解く連携
顎関節(TMJ: Temporomandibular Joint)は、下顎頭(下顎骨の関節突起)と側頭骨の下顎窩および関節結節から構成され、蝶番運動(回転)と滑走運動(前後・左右への移動)の複合運動を可能にする特殊な滑膜関節です。
この関節は、関節円板(articular disc)を挟んで上下2室に分かれ、
- 下関節腔:下顎頭と関節円板間で回転運動が起こる
- 上関節腔:関節円板と側頭骨間で滑走運動が起こる
というように、2軸的運動を分担しています。
◇ 側頭筋の関与
側頭筋は筋突起に付着し、その収縮は下顎頭の位置と運動方向に直接的に影響を与えます。具体的には、
- 閉口時:側頭筋の前・中部繊維が収縮し、関節円板と下顎頭を後上方に牽引
- 開口後の復帰時:後部繊維が関節頭を後方へ安定化させる
というように、関節の動的安定化と咬合の最終調整を担います。
◇ 不良咬合・習慣的な左右非対称動作による影響
不良咬合や片側ばかりでの咀嚼が習慣化すると、
- 片側の側頭筋に過緊張が起こり、筋突起が牽引される
- 結果として、関節円板の変位や**下顎頭の位置ズレ(偏位)**が生じやすくなります
このような状態では、関節内構造の協調運動が乱れ、以下のような症状が出現することがあります:
- 開口時の関節雑音(クリック音・クレピタス)
- 下顎の開口偏位(midline deviation)
- 閉口時の噛み合わせ違和感、関節部痛
また、関節円板の前方転位(anterior disc displacement)や、開口制限(closed lock)を引き起こすリスクも高まります。
このように、側頭筋の緊張バランスは単に咀嚼力の問題に留まらず、顎関節そのものの構造的健全性を維持する上で極めて重要な要素となります。
姿勢との関係:頸部・体幹への波及的影響
側頭筋や咬筋は、頭部の姿勢と密接に関係しており、特に頭部前方位(forward head posture)や猫背姿勢は、これらの筋に過剰な負担をかけることが知られています。これにより、筋緊張を助長する負のフィードバックループが形成され、顎関節や頸部、さらには体幹にまで影響が波及します。
◇ 姿勢不良が顎関節へ与える影響
頭部前方位とは、頭が重心より前方へ突き出る姿勢であり、デスクワークやスマートフォンの長時間使用で一般化しています。この姿勢では、
- 下顎骨は自然と後下方へ引かれた位置となり、
- 下顎頭が関節円板や関節結節に対して圧迫されやすくなる
- さらに、関節円板の位置安定性が損なわれやすくなる
といった変化が生じ、顎関節の微細な滑走運動が阻害される可能性があります。
◇ メカニズムの詳細
頭部前方位では以下のようなバイオメカニクス的変化が起こります:
- 下顎骨の相対的後退(posterior displacement)
- 顎を支える筋群(側頭筋・咬筋・舌骨上筋群など)に常に緊張が入ることで、顎の位置が後方にずれやすくなる。
- 関節内圧の上昇
- 後方への圧力が増加することで、下顎頭が関節円板および関節後壁に接触しやすくなり、関節雑音や痛みの原因となる。
- 側頭筋の過緊張
- 頭部を支える補助的な働きを担うため、側頭筋が常に収縮状態となり、筋性疲労やトリガーポイント形成を助長。
- 舌骨上筋群や頸部筋の協調破綻
- 顎運動時の安定性を支える他筋群との協調が崩れることで、嚥下障害や発語時の違和感を訴える例も見られます。
◇ エビデンス
Ishiiら(2015年)の研究では、猫背姿勢および頭部前方位姿勢では、咀嚼筋群(特に咬筋・側頭筋)の筋活動が有意に増加し、同時に筋疲労の蓄積や顎関節周囲の不快感が報告されました。これは長時間の不良姿勢によって咀嚼筋群が姿勢保持筋として代償的に働いてしまうことが原因と考えられています。
このように、側頭筋の過緊張や不調は、単なる咀嚼動作の問題にとどまらず、姿勢全体の歪みや運動連鎖の乱れに発展しうる重要な警告サインとも言えます。
まとめ
- 側頭筋は、閉口・後退・側方移動といった顎の三次元的運動を担う主要な咀嚼筋である。
- 解剖学的に扇状の構造を持ち、前・中・後部線維がそれぞれ異なる方向の運動に寄与する。
- 筋突起を介して顎関節の運動軌道に直接影響し、咬合バランスや関節安定性の維持に不可欠である。
- 不良姿勢や頭部前方位は、側頭筋・顎関節への負荷を高め、関節機能の破綻や疼痛の引き金になりうる。
- 筋緊張型TMDの評価・介入には、側頭筋の触診・運動観察・トリガーポイント診断が重要である。
- セルフケアや徒手療法を通じて、早期からの筋緊張緩和・顎機能の正常化を図ることが予防・治療の鍵となる。
側頭筋は見落とされがちではありますが、顎関節を安定させ、全身の姿勢や筋機能を支える中核的な存在です。患者の訴えが多岐にわたる場合こそ、この筋に注目し、全体像を俯瞰したアプローチを行うことが、臨床家として重要なことであると思っています。